橘健二、亮子、治国、太二、婦美子
橘健二1(朝日新聞記事その他),2(モーラ先生との思い出),3アマゾン「大鏡」,
家族のためのページ
for
my family
橘亮子
Ryoko Tachibana (9:05 AM July 22, Tokyo 1980年(昭和/Showa55年).
歌集「舞扇」古径社 Mai Oogi, Ryoko Tachibana
杉本清子先生
父も母も生前は大変お世話になりました。ありがとうございました。
_______________________________
挽歌
「舞ひをりて倒れしままに死にしとぞ無音すさまじき淵よりの声」
「床たかき能の舞台に舞ひながら倒れて果てぬ化粧(けはひ)の顔に」
「夢にまで舞ふと詠みしか舞ひながら倒れて世をば閉ぢたり君は」
「夏の日の照る寺庭は人を見ずきみが葬りといふ怪しき」
「日ざかりの石しろき寺の庭をゆく黒衣の裾を風ひるがへす」
「舞ひながら意識の去れば己が死も知らずありけむひとを驚く」
「脳波止みなほ心臓の生きゐたる終焉を言ひてその夫哭きぬ」
「暑かりし夜ふけて雨の太々と音するは深き穴へとそそぐ」
「舞ひをりて命終れるきみがうた精進(さうじ)とどめぬ夜の遠き雷」
「降りいでし雨の斉整の音ひびく夜になまなましひとつの急死」


母と恵美
自我強き娘孫にて着物ずき来付け習ふと洋服を脱ぐ
母さん。若い頃は反発ばかりしていたけど、母さんが1980年に亡くなって、もう今年で22年。
私の心の中の母さんの面影は消えていかない。一度はゆっくり話しができたらと思っていたのに。
あのころあまりに急に亡くなってしまった。いろいろと思い出されて、時折り胸に込み上げてくる思いは強くなる。そして不思議と年を経るにつれて父母兄叔父叔母いとこなど、時を共有した家族のことへの思いでなつかしくなる。自分も随分年をとったんだなあって思う。そして母さんが亡くなった年に近づいていく。
婦美子
父さん母さんが想像もしなかったサンディエゴにて。
2002年。

july2003
London
このお盆(2003年7月14日)に恵美に催促されてお墓(三重県四日市の泊村)参りをしてきました。四日市の建福寺で太ニ(次兄)と両親のために読経と供養をしていただきました。大変な雨の日でした。その後住職(Jr)さまご自身に運転していただき、父、母のためにまた供養をしていただきました。激しい雨でした。その年1980、母さんが鎌倉のお寺参りの日7月21日喉が渇いたと訴えた母さんだったそうだからこの時の雨は母さんのために降った恵みの雨だったのでしょう。
婦美子
舞扇
(工事中)
目次
昭和五十年
蟋蟀 11
レストラン 15
昭和五十一年
鰰(はたはた)21
受話器の声25
球根 28
歌碑 31
書庫建てて34
山脈<阿蘇雑詠>37
秋立つ40
夢43
昭和五十二年
ロングスカート51
紫式部54
蕾(つぼみ)固く57
なぜにためらふ60
啓螢63
薬師寺にて66
潮騒70
木蓮74
粽巻かんと77
兄84
昭和五十三年
地鎮祭98
父と兄
眠る呪文
春めく
夢ひとつ
明暗
天突き体操
汗
野の花
昭和五十四年
大事に蔵ふ
庭の菊
雪
身めぐり
秋田
二人住みつつ
転居
街の鶏
取柄なき
浦和
栗の実
謡ひつつ
昭和五十五年
母
家整へて
三家族
移る
公園
師のまなこ
夢にまで
ゆすら梅
眠られぬ時は
挽歌 杉本清子 1
跋 杉本清子
あとがき 橘健二 203
********************
(「長風」投稿)
蟋蟀
座敷まで上がり来たりし蟋蟀の暗きに寄りてころころと鳴く
一冊の歌集読み終へて仰ぐ空静かに移るうろこ雲見ゆ
一人居の部屋の広きに目覚めゐてこの耐へ難き夜のしじまよ
幾度も目を覚ましつつ一人居の淋しき夜を眠りのみ欲し
家族らを思へるのみに生きしわれ大正生れ嫁そして姑
影踏みを孫に教へて歩くわれ子と遊びしも昨日のごとし
夏の夜に飛び来る虫の我が白きノートの上に生を終ふる
バラの木に日々の手入れの怠りを示すがごとく小花群れ咲く
待ち待ちし実生の椿十年のとき経て今日は蕾をもてり
父と子と静かに話しゐたりしが子はつと立ちて涙かくせり
豪雪に枝割れてなほ生きて来し柿の一木が台風に倒る
レストラン
故郷の母の手作りにんにくの薬とどきぬ八十路の母は
細やかに薬の分量なども書く母の便りは薄くあたたか
-おばあちゃん(キギ祖母)の着物のすそにしがみついてないたこと、よく覚えています。おばあちゃんは、よく「そやに」って笑って。
活花の競技の花の枝折れぬ全身に汗の一度に噴き出づ
大けやきの根方に建てるレストラン夫の好みて誘へば従い来
わが好むコーンスープをすすりつつ川に秋雨の打つを眺むる
玄関に不意にだるまを売りに来ぬためらはず二個を何ゆゑ求めし
高く伸び紫苑の咲ける空晴れて飛行機の音も秋の音なり
峰吉川村ひくき静まりて薄紅葉せる道を登りつ
昭和五十一年
鰰(はたはた)−−秋田名産
地響きの音すさまじき雷をラヂオは告ぐるはたはた郡來と
鰰寿司口になじめば待ち遠しはげしき雷もいつか親しく
今これを詠まんとしつつ歩みゆく不意に電柱目の前にあり
華やかなパジャマ求めて店の娘に手足の冷えを防ぐためと言ふ
今一度庭掃きおきて春待たんと思ひてゐしに今日のこの雪
時折は椋鳥の来て柿の実に太き嘴ふるふがをかし
椋鳥の嘴(はし)荒ければたちまちに柿の実落ちて雪に埋もりぬ
朝はなきベルに驚き出で見れば鰰持ちし男鹿(おが)の人立つ
自らが漁りしといる鰰は朝の光にかがやきを持つ
鰰を厨に置きて青年の立ち去りしあと大き雷鳴る
元日に寒梅の一輪部屋うちに綻びしこと頼まんとする
浮標ありて漁夫はボートを近づけぬ暫く覗きやがて去り行く
受話器の声
書を習ふ八十路の母ゆ遠慮げに落款欲しき意味の便り来
受話器より遠き記憶の声聞こゆ薬師寺の高田管長のこゑ
受話器より伝わる声は高田さん 若かりし日と変わることなし
薬師寺の塔を仰ぎて経し二年貧しきに耐ふる戦後なりにき
-
父は論文書きで忙しかった。母は苦労したということはよく聞かされていた。
春の日のまぶしき窓辺鉢植えのピラカンサスは白き花咲く
空晴れて庭に残りし雪の上鳶の落とせる影のすぎゆく
雪解けの庭となりつつ不器用に我の囲ひし木々あらはるる
街角に宝くじ買ふ人の列友と見て友と過ぐあたる事なし
ブームなど何のことなしと思へるに口遊(くちずさ)みをり鯛焼きくんの歌
球根
黒々と光れる薬師如来なりその前の人管長親し
東北の球根なれば東京に移せど春は遅しと笑ふ
三十年いまだ一度も出でざりし学級会の知らせ来たりぬ
子を負ひしネンネコ半纒孫をいま負ひて寝息のたつを聞きゐる
老二人暮す我家に幼来て台風のごとく幾日かあり
はら赤き鳥の来る日は息潜め見んとしてをり一瞬楽し
遺言書我に渡して笑ふ夫その眼にかすかに淋しさのあり
歌碑
五十幾年世の荒波に晒されし落着き見せて友等の集ふ
紺袴召しまさねどもにこやかに変わらざる師のまなざしに会ふ
共働きする娘の家に立ちよりて誰もいゐぬまに大掃除なす
つとめより帰る娘はうれしげに稀には来よとてれて礼言ふ
-世話になってばっかりでしたね。
秋田より刈和野駅まで一時間をみな三人かしましく行く
静けきにまたのどけきに沼の辺の歌碑は桜につつまれて立つ
幾度かあきらめきれず挑む子の司法試験日迎へて今日は
書庫建てて
数ふれば五年目にひくわれの風邪胃腸を守り薬を飲まず
初夏の日の強く射しをり睡蓮の葉は水面にひとはりつく
屋敷内草ひき終へて十日程風邪に臥せればまたも生えゐる
書庫を建て畠なくしぬトマト茄子植ゑずに居るは心淋しき
花終わるさつきどうだん移し替へ夏野菜苗数本を植う
歩の遅きわれを追ひつき行きし人信号待ちにて再び並ぶ
。。。
秋立つ
レントゲンの結果を待てる一日を医師の言葉の裏のみ思ふ
戦災に遇ひたる我が子は病みき冷たかりし医師を未だ許せず
さらさらと袖に触るるは秋の風不意に淋しさ湧くは老いしか
夢一つ見しことなくて淋しといふ夫の寝息を聞きて拘る
亡き父のわれにたまひし鉄瓶をふとしも思ふ秋立つ今日は
鉄瓶の湯をたぎらせて蓋をきる父の所作に似ていつか身につく
合歓の花淡々と咲く象潟を過ぎて入日は並に燿ふ
我が成せる舞子姿の紙人形欲しと言ふ子にもらはれ行きぬ
夢
あかつきの電話のベルは産院の娘入りたるを知らせて切れぬ
身の廻り整へ「長風」一冊持ちて旅立つ小雨の朝に
満潮と出産のことふと思ひ落ち着かずゐる娘に関りて
。。。
夢一つ見ぬは如何なるさまなりや我の眠りは夢のみつづく
。。。
昭和五十二年
ロングスカート
頑固をば老の勲章と看護して励む姉なりこのおほらかさ
歌の稿書き終へて午前三時なり心安けくめぐりを整理す
若き日に疎みて永く読まざりし「歎異抄」を出す心弱ければ
時雨るる日長く続きて故郷の明るき空と亡き父母思ふ
昨夜遅く野分過ぎたる我が庭の紫苑コスモス地に乱れ伏す
。
ロングスカート身になじみつつ快し家に籠りてゆらゆらと居る
紫式部
落葉してその色淡く結ぶ実を紫式部と聞き手佇む
我が夢の住ひは折に故郷の亡き父母おはす寺の庫裏なり
叔父よりの手紙は厚く亡き母の遺言状なり四十年経し
新しき家立ち並ぶ間より雪斑らなる手形山見ゆ
時雨るれば空の暗しと惜しみなく窓に寄る木の枝切り落とす
枯れ枯れと。。。
。。。
なぜにためらふ
雪国より出でて来しかば東京のビルの間のかぜ肌になじまず
我が土地に立ちて見放くる鈴鹿山つひの栖をなぜにためらふ
。。。
啓蟄
屋根の雪氷塊となりてなだるれば大地とどろき厳寒つづく
玄関に屋根より落ちし氷塊の解けずゆるがず啓蟄の来ぬ
風未だ冷たけれども軒に積む雪は陽射しに解けてくづるる
亡き母の齢を超えて二十年いま母のごと短歌に凭りぬ
我が母の日常は人のものなりきあまえし事の無きを淋しむ / 母の兄 ryoshotakatomi.htm
何のために習ふ活花か自らの年を数へて馬鹿とも思ふ
憤りおさへて街を歩みつつ買い物終へぬややに落ちつく
老いそめていま気短かになりし夫静まるを待つせん方もなし
。。。
薬師寺にて
関西を夫と旅するみちすがら我一人にて薬師寺に来つ
西の京のホームに立てば若き日の我の姿のあざやかにあり
三十年たちて来たりし奥柳古き農家のあるに寄り行く
勝間田の池より尚も西に行く金堂をひとり振り返りつつ
冬の日の短きときを歎きつつ夕暮れせまる薬師寺に来ぬ
輝ける金堂の扉開けるを気安く入れば蝋燭ゆらぐ
南大門出でて歩みぬ八幡宮かつて住みし家そのままにあり
苦しみの重なりて経しこの家を懐かしむまで歳月の経ぬ
夕光の幽かに及ぶ水煙を仰ぎてゐたり立ち去り難く
門前の店を覗けば主ゐて変わらぬ顔に笑みを返しつつ
。。。
潮騒
。。。
姉夫婦夫と西ゆく旅なれば一歩下りて我の座はあり
兄も夫も共に老いたり旅の夜に幼日話すことを証しに
父と兄
。。。
病院を出て立ち寄りしデパートに冬物値下げの札賑々し
一人一人いづれ死は来るものにても兄若くして年の瀬に逝く
長かりし療養の日を弱気など人に見せずに毅くして逝く
眠る呪文
。。。
春めく
娘が摘みし芹を加へて朝餉とす旅の心のほぐれぬままに
団地内の八百屋に入れば先に住む女らの鋭き視線に出会ふ
故郷に父あれ兄あれと願へども逝きし人らはせん方もなし

自我強き娘孫にて着物ずき来付け習ふと洋服を脱ぐ
-恵美
やうやくに着付け終へたる娘の姿棒に着物を着せたるごとし
-これは「婦美子」
。。。
夢一つ
。。。
幸せと思ふ日にして殊更に淋しさの増すこの現身は
修羅なせる生さぬ家族と共に住み飄々とははの日日はあり
。。。
燃えさかる家より幼背負ひ出す動悸残りて夢より覚むる
みる夢に疲れの残るこお多し心貧しきおのれ哀れむ
亡き母の齢を我は遠く過ぐうつしゑ常に三十五歳
夢にまで舞ふ我あはれ初舞台終わりて藤の花房に寄る
折々に会へば死にたしと老母の言ふを淋しく口癖と聞く
亡き父のわれにたまひし鉄瓶をふとしも思ふ秋立つ今日は
わが夢の住まひは折に故郷の亡き父母おはす寺の庫裡なり
過ぎし日は楽しくありぬ眠りにては夢一つ見ぬ不思議な夫と
亡き父母を恋ふる句多し八十を過ぎたる母の衰へ著しく
精一杯なさんと覚悟するときに泣き父の言葉 取柄なきお前は
作歌が時に苦業であったことを物語る歌。趣味の範囲を超えて歌を書こうとすれば勢い苦しい日が誰にも来る。。。(杉本清子先生)
老母の修羅なす内を思ふ夜蛙の声は我が家をつつむ
道端の垣根となせるゆすら梅口にふくめばなまあたたかし
「ひそやかな秋を移さん我が部屋に薄野の菊器にあふれ」
「薄野の菊器にあふ」と詠った秋の亮子さんは再び巡りあうことなく世を去るが、この最後の秋はまた師鈴木幸輔にとっても終わりの秋であった。師は亮子さんの歌にこめられた生きづきの静かさを、どの様に見守られた事であろう。
「先生、六十歳の時には歌集を出したいと思いますができるでしょうか。」
「ああ、大丈夫ですとも。しっかりおやりなさい。」
遺稿集を編むことが決まってから、夫君の国文学者健二氏からお聞きしたこんな会話を、私はその秋の師と亮子さんの間に仮定してみる。
師は亮子さんの上にさらに数年の時間を望見し、無垢な一個性の開花を、新しい歓びとして願われたに違いない。しかし時は縮まっていた。翌春のサクラを見ずに師は逝き、追うようにして亮子さんも世を去った。何の予告もない死であった。能のお舞台で舞いの稽古中に倒れて意識を失い、そのまま不帰の客となったのである。六首目の「夢にまで舞ふ我あはれ」の歌は五十五年七月号に出詠されたもの。藤の咲く五月上旬のその舞台はあったのであろう。夢にまで稽古を積んだ初舞台の終わった安堵と、まだ残る心身の熱きを藤の花の静かさに寄せるこの一首は、豊かでかつてない艶を含む。
翌八月号」の詠草を受け取った時に私は眼を見張った。敬慕する師の死に逢い口ごもるさまに見えた言葉の流れが変わり、歯切れ宵軽やかさが歌全体にあふれていたからである。十首残らず採って「よい調子ですね」と私は書き送った。
翌月の詠草は七月十九日に届いた。死の三日前である。走り書きが添えてあった。「十首できましたのでお送りいたします。よろしくお願い申し上げます。先月は出来がよかったとおっしゃってくださいましたので大変作りにくく、困りました。」しかし送られてきた歌は前月に劣らずよいものであった。
「眠られぬ時は逆らふことのなくひとりベランダに夜の街眺む」
「ゴーゴーと夜空にこもり音するは甲州街道を走る車か」
「晴るる夜の一人覚める午前二時シグナルの点滅規則正しく」
「軋むおと舞台に起こる地震(なゐ)のなか静かにシテの舞ひはつづきぬ」
。。。
今日まで何回もこの最後の歌を読んだ。読む毎に亮子さんの気持ちが乗り移ってくるような切なさを覚える。これは歌のお仲に作者の生がなまなましく定着しているからであろう。。。。この最後の姿を私は愛惜してやまない。。。。
あとがき 橘健二
荊妻亮子が東京水道橋、宝生流濤松回松本忠宏先生のもとで稽古中に突然意識不明(蜘蛛膜下出欠)に陥りましたのは、昭和五十五年七月二十一日(月)午前十一時で、そのまま翌二十二日午前九時五分日本大学駿河台病院にて、五十八歳を一期として永き眠りにつきました。生前亮子のためにお与え下され師御厚情の数々に深謝申し上げるばかりであります。
ここに亮子の生前に詠んだもののうち「長風」掲載のものを、杉本清子先生のお手を煩わし抄出、取りまとめました。秋田在住(昭和39〜昭和54)の時に、赤木美津子さんがたと秋田強首ご出身の鈴木幸輔先生の「長風短歌会」に入れていただきました。れまでは奈良在住時代に前川差美雄氏婦人緑氏選の大和タイムス新聞社短歌欄に時折投稿しておりましたが、むしろ春日野俳句会に属し、岨静児氏・奥野静山氏らと共に俳句に励んでおりました。「長風」にひあってからは、ひたすら作歌に明け暮れ、鈴木先生はいつも暖かく且つ厳しく激励してくださり、亮子は別人のごとく歌に真正面に向かいました。足掛け六年、約500首の「長風」掲載短歌は、日々苦しみつつ楽しみつつ物下身辺雑詠であります。私との二人の生活、子どもたち、親戚友人ないしはその周辺の生活記録であり、雄見苦しい数々ですが、かけがえのない日々の記録としてまとめた次第であります。
幸輔先生が同じ年の四月に御他界されてからは、日の浅いのにも拘わらず、杉本清子先生に親身になってお導きいただきました。作歌の心を鍛えていただき、亮子の歌心は一段と深まりゆくまま、まさにこれから一層の努力をという時期に差し掛かりましたが、忽然としてこの世を去っていきました。
私はいま、あまりにも自分の仕事にかまけすぎたことを後悔しております。いつも。。。
つづく
昭和五十六年六月十六日 於 国立寓居)
過ぎし日は楽しくありぬ眠りては夢一つ見ぬ不思議な夫
母は父のことを詠んでいます。今、母が歌を詠んだと同じ齢ような歳になり母の思いを理解しようと思うようになりました。また今ごろになって母のことを知りたいと思うようにもなりました。母はかなり消極的な人でしたが逆に父は上の歌で詠われているように赤鬼で、気が短い割に後で根に持つことはありませんでした。父のように残りの人生を前向きに、父のように幼子のように生きていきたいものだと思っています。父は本当に過去のことを思い出さない不思議な人でした。本当に私はかわいがってもらったと思います。その中身は、いつも教育者らしく「終わったことはよい。今度がんばれ。」これだけで励ましてくれました。父からしかられた記憶がありません。母は冷めた愚痴ばかりこぼしていたという記憶しかないのです。でもこれは母自身の成育体験がもとになっていると思います。実母が35歳の時に亡くなったことにもよるものでしょう。歌によまれているように、祖母は大変慕われていた小学校の先生であったということから、甘えさせてくれる母の存在はなかったようです。つまり、私が母に対して抱いていた冷たい印象というのは、母としてのモデルが母自身になかったからではないでしょうか。また、その母が没後40年もたってから母の遺言状がとどいた、と詠まれていますが、その手紙の中身はだいたいの察しがつく程です。ついでにその祖母は名前を豊といい、いとこの文祥さんからいただいた手紙によると今でもその豊先生を慕って懐かしく語ってくださっているかたがいるそうです。
ずっとやさしく何があっても応援し励ましてくれた父親への印象が強かったのですが、母の短歌を詠んで少しずつ母を理解できたことはうれしいことです。(この20年読む気持ちにはなれませんでした。)この影には母の努力を、常に励ましていた父の存在を思います。
終戦後、西ノ京での生活は相当きびしかったようですね。母は苦労話ばかりしていました。千葉の家がやかれたことが関西にくるきっかけになったそうです。多分大学の先生になる予定で一生懸命論文を書いていたんじゃないか、って今ふと思います。当時奈良女子大に招いてくれる予定だった教授が亡くなり父の人生は狂ったとよくいってました。付属に16年お世話になることになってしまったが、付属ではよくしていただいた、ということでした。しかし、雷先生として名をはせよく教職員とは意見の衝突がありよく喧嘩していたらしいです。鈴木先生によれば、そうとう「変人」の父だった、らしい。学校では三人の子供全員父を避けていました。(ただ喧嘩をしてもすぐに仲良くなると自負してました。。。)
この苦しい経験のお陰で、橘大鏡はナカムラくんによれば「
nakamurakun.htm 。
このページは、自分、自分の子供たちのために作っていま。
婦美子私とって貴重な写真。

太二、母、私、治国
中村君父を語る、奈良で思い出。

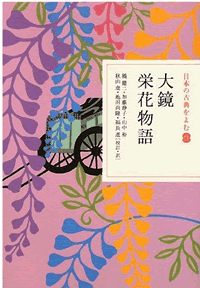 Amazon
/これは母が応援した父の著書が進化した改訂版)
Amazon
/これは母が応援した父の著書が進化した改訂版)